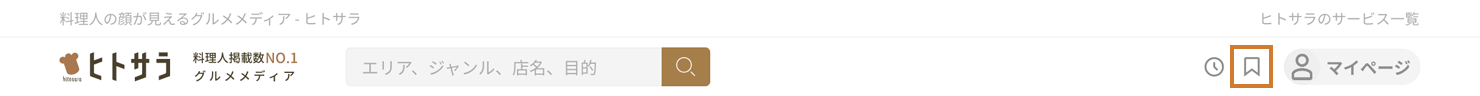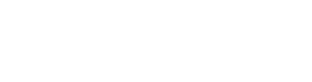ゲストの記憶に残る秘密は、“空間と料理の同期”にあり!?
 【Ode】のスペシャリテ、『鰯 尾崎牛 黒ニンニク』
【Ode】のスペシャリテ、『鰯 尾崎牛 黒ニンニク』
――グレーの店内、そしてグレーのスペシャリテが印象的です。お店をつくるときに、グレーをテーマカラーにしようと決めていたのですか?
最初から決めていたわけではないのですが、店のインテリアのキーカラーは料理に集中してもらえるような無彩色にしようと思っていました。もともとグレーが好きだったので、店内は温かみのあるグレーをベースにしようと設計士さんと意見が一致。そのときに店内の工事と同時並行して、スペシャリテ用のオリジナルの器を作る相談を有田焼のカマチ陶鋪さんとしていたんですね。「スペシャリテはどんな料理なんですか」と聞かれたときにはまだなんにも決めてなかったんです。でも、食材を無駄にせずに全部使いたくて、青魚のフィレの部分を使った後に残る頭や骨を利用した料理ができたらなと漠然と思ってはいました。魚のアラの部分をミキサーにかけてメレンゲと合わせて焼いたらグレーになるということは知ってましたから、それを利用して、店内のグレーのトーンと同期させられるようなスペシャリテができるかも、と思いついた。誰もやってないし面白い、と思ったんです。
 左/個室 この照明の形がデザートのインスピレーションに。 右/デザートの『リンゴ 白ビール』
白ビールの泡に包まれたりんごのコンポートをさらに飴細工で覆っている。台湾のハーブ、マーガオの香りをまとわせて
左/個室 この照明の形がデザートのインスピレーションに。 右/デザートの『リンゴ 白ビール』
白ビールの泡に包まれたりんごのコンポートをさらに飴細工で覆っている。台湾のハーブ、マーガオの香りをまとわせて
――店内のインテリアと料理を同期させる、というのは面白い発想ですね。
もともと、“いろんな食材が皿の上にたくさんあっても一つのものになっている”というのがやりたい料理の方向性です。空間も同じ。モルタル、木、ステンレスと素材感の違うものを使った集合体だけれど俯瞰すればひとつの世界になっている。その延長上に、空間と料理も同じ世界感にある、というのは意識しています。僕はお客様に気分がいい空間で食事をしてほしい。だから自分が“気分がいい”と感じる色を使い、好きな木のぬくもりある家具を配置し、好きな音楽をかけて心地良さをつくる。ゲストが空間にいるその“心地よい感覚”と料理が同期して、一つの世界観になることをイメージしています。
このデザートも、フォルムは個室のトム・ディクソンの照明と同じ形に作ったんです。これも「空間と料理を同期させたい」と思って生まれたもの。目にするもの、口にするものが一緒になることでレストランでの体験を印象的にできるかなと考えました。
 【Ode】名物、アミューズの『ドラ〇ン ボール』。カカオのコーディングの中にはオマールのビスクが
【Ode】名物、アミューズの『ドラ〇ン ボール』。カカオのコーディングの中にはオマールのビスクが
――スペシャリテも、このデザートも、最初に出てくる『ドラ〇ン
ボール』もひと目見たら生井さんの料理だってすでに認識されてますよね。「誰が見てもこの店の料理」というものを考えようと意識しましたか?
それはすごく考えました。誰もが見て“ここだけの料理”というのは絶対に作ろうと思っていました。今はSNSの時代で、料理のヴィジュアルのイメージが一人歩きして世界中を駆け巡る。その写真を見て世界から人が訪れてくれる時代ですから、そのイメージの拡散は意識しましたね。けれど、“こんな料理をつくろう”として明確なものが初めからある訳ではなくて、楽しんでやっているうちに、面白いものができる、という感じですね。
メレンゲのスペシャリテも先ほど話したようにお皿の制作と内装工事の話のなかからヒントがでてきて、そこに昔から好きだった山海の食材の組み合わせを考えて尾崎牛のタルタルを合わせています。『ドラ〇ン
ボール』も、オマールのビスクをカカオバターで作って球状にできないか試作していたら、キレイなオレンジ色のものが出来て。「これ、ドラゴンボールみたいじゃない?」と厨房で盛り上がって、「じゃあ星描いてみる?」、「クッション置いてみる?」って遊びながら誕生したんです。店で出したら30代から40代の男性の受けがめちゃくちゃいいですね。
――おもしろい! 色彩も食感もいろいろ緻密に考えてつくられているような気がします。
できるだけ視覚に入る要素は少なく、と思っています。視覚情報をそぎ落とすことで他の感覚が研ぎ澄まされる。先ほどのスペシャリテのメレンゲの下には赤い生肉。突然現れる赤い生肉に、官能的な本能が揺さぶられるんじゃないか、と考えたりするんです。あと、人間って隠れているものを見るの、好きじゃないですか(笑)
また、食感についても考えます。料理はレイヤーで重ねていて、それを全部いっしょに食べてほしいんです。歯ごたえを生む食感からはリズムが生まれます。そして咀嚼しているうちに縦のトーンが現れて、硬いものはそのトーンのなかのアクセントになる。食べたときに口の中でどうなるかを考えて盛り付けをします。
ミュージシャンから料理の道へ。そして軽井沢で訪れた転機
 盛り付けなどをライブで見ることができるカウンターは、まさに【Ode】劇場の特等席
盛り付けなどをライブで見ることができるカウンターは、まさに【Ode】劇場の特等席
――言葉の選び方が、やはり音楽をやっていた方ならではですね。昔ミュージシャンだったと伺いました。そこからなぜ料理人へ?
料理人を目指すようになったのは遅いですよ。もともと法律専門学校に通っていて地方公務員を目指していたんですけど、試験に落ちちゃって。卒業後はサラリーマンになって営業職につきました。けれど音楽の道をあきらめられなかった。
僕はローリング・ストーンズのコンサートで音楽にハマったんですけど、彼らが影響を受けたルーツミュージックに惹かれて。で、会社を辞めて当時ルーツミュージックの聖地だった船橋のライブハウスで活動するようになったんです。そのライブハウスのマスターが元フレンチの料理人で、彼の手伝いをするうちに料理に興味を持つようになりました。思えば母親も料理上手で友人が遊びにくると実家の料理が好評だったのを思い出したりして「料理をつくるって素敵だな」と思いました。しばらく音楽活動をしていたのですが「この人には叶わない」という人が星の数ほどいて、自分はこの世界で何やっているんだろうと疑問に思うことが増えたんですね。料理の世界なら、小さくても何かできるのかもしれない、そんな風に思って料理人になろうと決めたんです。
――それはまた大きな決断ですね。そしてフランス料理を選んで、料理を学ばれたんですか?
お世話になったライブハウスのマスターが元フレンチだったことからなんとなくフレンチに興味を持ちました。いくつかのレストランで働いて基本的なことを学び、【レストランJ】に入りました。そのときに植木将仁シェフとともに軽井沢の【マサズ】に移ったことが大きな経験でしたね。それまでは電話一本で食材が手に入っていたのに、野菜一つとっても毎朝畑で収穫させてもらうことから始まりました。
そのことで、「この季節はこの食材だな」と頭で考えていたことが払拭された。例えば季節によって同じ野菜でも大きさも味も違う。イメージしていた味とサイズが違ったりするんです。だから「じゃあどうしようか?」と考える。食材を多面的に見ることができました。さらに、東京では扱えないハーブや、川魚、自分で収穫したきのこなんかも使えた。自分で足を運んで収穫したものってやっぱり愛着もあるし、農産物を生産するという大変さもわかりました。
 ソースは必須という生井シェフ。「ソースを合わせて生まれる新しい発見をしてほしいですね」
ソースは必須という生井シェフ。「ソースを合わせて生まれる新しい発見をしてほしいですね」
ゼロからつくる自分の理想の店で、様々な想いを伝えていく
――その【マサズ】を引き継いで【ウルー】という店名に変えてシェフに就任。その後【シック・プッテートル】を東京でオープンしたんですよね。
軽井沢が面白すぎて、植木シェフが東京に戻ることになったときに残りたいと言ったんですね。そして、【ウルー】で【シック・プッテートル】のオーナーと出会って、東京で店をやらないかとお声がけいただきました。当時のオーナーからの要望は「ビストロ」的な気軽な雰囲気でもきちんとした料理が食べられる店を作りたい、ということだけ。5年ぶりに戻った東京で好きにやらせてもらえて、店名も自分でつけました。当時パリは“ネオビストロブーム”で、ビストロでもガストロノミーの料理を出す店が流行してました。僕もビストロだけど料理はガストロノミーを出したいと思っていた。だから「シックかもね?」という意味で【シック・プッテートル】と名付けました。イメージは当時人気だったパリの【セプティム】みたいな感じでまずはスナック感覚のものを出してワインを楽しんでいただいている間にメインを作るスタイルでしたね。サービスが一人に、料理人も一人だけど最高の料理を出したい、とオペレーションもかなり考えました。
――自分自身の店をつくろう、と思ったきっかけはなんだったのでしょうか?
店をやりながら、もう一段上がりたい、と思うようになりました。そして、なによりゼロから思い描く理想の店をつくりたいと思ったんです。独立をすると決めて1年半。物件は2カ月半くらい探して出会いました。
 この日届いた食材の一部。「国東オイスター」、「梶谷農園のハーブ」、「京都・伊弥栄の鴨」、「能登・高農園の野菜」など。「この鴨は肥育している鴨なのにみずみずしくてジューシー。日本人が好きな味ですね。この牡蠣はクリーミーというよりクリアな味わい」と、食材について話しだしたら止まらない生井シェフ
この日届いた食材の一部。「国東オイスター」、「梶谷農園のハーブ」、「京都・伊弥栄の鴨」、「能登・高農園の野菜」など。「この鴨は肥育している鴨なのにみずみずしくてジューシー。日本人が好きな味ですね。この牡蠣はクリーミーというよりクリアな味わい」と、食材について話しだしたら止まらない生井シェフ
――自分の店をやるならこういう店、というコンセプトはあったんですか?
日本の食材で料理をつくる、というのは決めていました。僕はフランスでの修行経験がないですし。日本のお客様はもちろん、海外からも自分の店を目指してきてほしかったので日本のいい食材で日本のフレンチをつくりたいと思いました。日本には志のある素晴らしい生産者さんがいる。その思いもあわせて海外の人に伝えたいと思いました。
ですから、使う食材は生産者さんの顔がはっきりと見えるものを使います。もともとの取引先、知り合いの方の紹介、そして売り込みにいらっしゃる方もいますが、そこが共通ですね。店名の【Ode】は抒情詩という意味なんですけれど、この場所は自分の想いを伝える詩、そして生産者さんの想いを伝える詩、自分の料理を伝える詩、様々な想いを詩のように伝えたいと名付けました。
 だしでさっと火を通したはまぐりの上にはゴーヤの泡。菜の花の苦みを生かしたニョッキははまぐりのだしやバターをあわせた菜の花のピュレが。ホタルイカのペーストが隠し味。これぞ”日本の春”を感じるフランス料理だ
だしでさっと火を通したはまぐりの上にはゴーヤの泡。菜の花の苦みを生かしたニョッキははまぐりのだしやバターをあわせた菜の花のピュレが。ホタルイカのペーストが隠し味。これぞ”日本の春”を感じるフランス料理だ
――これからは、どんなことをやっていきたいですか?
夢だったお店を持てたので、レストラン・食のシーン全体の厚い層をつくる一員になりたいですね。音楽でもルーツをたどることが好きだったのですが、料理もそう。ルーツをたどった上で温故知新、時代の空気感をキャッチした料理をつくりたい。去年と今年では時代に流れる空気が同じわけがない。絶対に違うんです。だから新しいものを柔軟に受け入れ、今の時代にフィットするように形にするのは必然だと思っています。
実年齢ではなくて感性が大切。自分のアンテナがそれをキャッチできなくなったら「ジジイになったんだなあ」と思いますよ(笑)。そうならないためにも、自分のアンテナの感度は高くしておきたいですね。
撮影/岡本 裕介 取材・文/山路 美佐(2018.3.7取材)